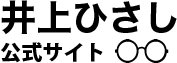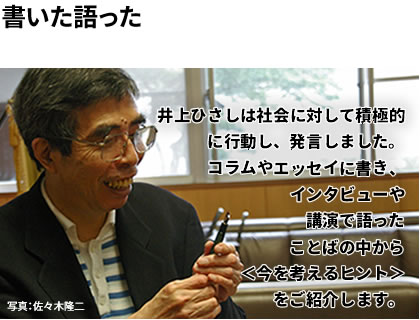NEW!
![]() 1989年執筆
1989年執筆
作曲家ハッター氏のこと
一人の人間の生死によって、時間に「明治」だの、「大正」だの、「昭和」だのといった枠をはめられるのはいやだ。そんなものでわれわれのかけがえのない時間を勝手に区切られたくない。そう考えているので、昭和が終ろうが、平成が始まろうが、なにひとつ特別な感慨がない。昭和回顧はそういうことのお好きな向きにおまかせして、私は読みたい書物をゆっくり読んでいたい。――以上で私の感想はおしまいだが、これではあんまり曲がない。小学生のころの思い出話をひとつして、責を果すことにしよう。
生家は田舎の薬局である。文房具や書籍雑誌も商い、レコードも売っていた。昭和十五、六年(こうやっていちいち年号を書かねばならぬのは、いつものことながら苦痛である)になると、蓄音機用の鉄の針は姿を消した。かわりにピックアップに竹針をさしこみ、その尖端でレコードの溝から音を取り出していた。店の一角で、この竹針が小山に盛られて客を待っていた光景がいまでも眼の底にあざやかである。レコードの枚数は割当制だった。売れたから追加注文、という具合には行かぬ。人口六千の田舎町には高峰三枝子の「湖畔の宿」は二枚しか出せないというふうに、向うから数を限ってくるのだ。レコードは入るとすぐ売れた。そこで私たち流行歌好きの子どもは忙しい。その日のうちにレコードを聞いてしまわなければならぬ。ぐずぐずしていると聞き逃してしまう。母親から「お客様にお渡しする前に一回だけ聞かせてあげる」という許可が出ていたので、それをあてにして近所の好きものの子どもがこっそり集まってくるわけである。
もっともなかにはひと月もふた月も買い手のつかないレコードがある。土地柄のせいもあってか、洋盤レコードは売れ行きが香しくなかった。そういった洋盤のなかで忘れられないのは、「私の好きなワルツ」という曲だった。軽快だが、どこか哀愁を含んだ旋律をスチール・ギターやバイオリンやアコーディオンが何回も繰り返し、おしまい近くになって男声が英語でうたい、口笛がそれに続くという構成であったと思う。これを毎日のように竹針で聞き、聞くたびに好きになり、みんなで口笛を吹けるようにまでなった。「作詩ハッター・マクスウェル、作曲ハッター」というラベルの文字もおぼえた。このレコードと私たちとの蜜月は三ヶ月ばかり後、町の図書館長がこれを半値に叩いて買っていってしまうまで続いたのだが、ついこの間、作曲家服部良一の自叙伝を読んでいるうちに、「ハッター・マクスウェル」も「ハッター」もともにこの人の変名だったと知り、仰天してしまった。
事情はこうである。このレコードの発売は昭和十六年七月だが、そのころ輸入制限措置がいちだんときびしくなって洋楽原盤の輸入が極端に減った。そこで国内でつくった偽の洋盤が出回り、服部良一はそうした偽洋盤のヒット・メーカーだった。軍国歌謡の苦手な彼は、こうした変名で口を糊していたのである。才能のある作曲家が変名で仕事をしなければならなかった時期が昭和という時代にあったこと、そういったことが頭に刻みつけられているあいだは、少くとも私は昭和という年号を使うことに抵抗を持ちつづけるだろう。
「餓鬼大将の論理エッセイ集10」
(中公文庫)に収録

Tweet