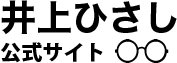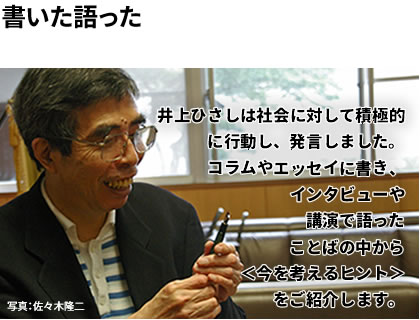![]() 2008年3月30日 朝日新聞掲載
2008年3月30日 朝日新聞掲載
新聞と戦争
――― メディアの果たす役割は
深みのある歴史分析こそ
戦争についての私の記憶は1940年に始まる。当時の私は、国民学校への入学を翌年に控えた子供だった。
我が家は朝日新聞をとっていた。私は新聞が好きで、そこに書いてあることは本当のことだと思っていた。
新聞はあの戦争を正義の戦争だとうたった。国家にとって不都合な情報は、情報局や軍の報道部に抑えられて報道しなかった。それらの点で新聞には、いわゆる戦争責任があると言える。
だが、あのときの新聞に「この戦争は間違っている」という批判が出来ただろうか。当時の私自身の感覚に照らせば、無理だったと思う。軍部の力は強く、「全体戦争」の状況下では新聞も国家に動員されていたからだ。
そうなってしまう以前、まだ批判を書けた時代にもっと頑張れなかったか、がポイントだろう。浜口雄幸内閣(29~31年)の時代がそれにあたると思う。当時は国内にも「国際協調が大事だ」という機運があり、軍縮を進められる状況もあった。
植民地をぶんどるのではなく、国際通商によって生きていこう。当時もあったその考えを新聞がもつと強く書いてくれたら、満州事変(31年)以降の戦争への流れは止められたかもしれない。
戦争とメディアの歴史から私がくみ取る教訓は、仮想敵(国)を作らないことだ。
戦前、中国などを仮想敵にして対外強硬の主張をする人は人気を博した。逆に近隣国との協調を説く人は「軟弱だ」などと批判された。
「風」の問題もある。私が東京裁判の芝居を書いたときに一番困ったことは、戦時中は皆が「聖戦だ」と騒いだはずだったのに、戦後に「あのとき騒いだ一番の責任者は誰だ」と探すとそこには誰もいない、という問題だった。
その時々の「風向き」がメディアや人づてで広められるうちに風が大きくなり、誰も逆らえないほどに強くなった。「みんながそう言っている」という"風向きの原則"が働いたのだと思う。
危ない国だと敵視する流れが風になり、「やってしまえ」まで行ってしまう前に、流れの内実と他国の実情を調べて知らせる仕事は、新聞の独壇場であるはずだ。
つるつるした「時代のキーワード」が作られて皆が一方向へ動こうとするとき、過去と未来を考えて深みのある分析の言葉を作ること。新聞にはそれを期待したい。今を伝える記事と同時に、10年後の未来を中期的な視点で考える記事や、50~100年の長期的視点で歴史の大状況を考える記事を載せることだ。
満州事変で朝日はなぜ、軍の中国侵攻を追認してしまったか。取材班は総括で、「ペンを取るか生活を取るかは、ジャーナリズムとしての覚悟の問題に帰する」と書いた。
だが私は、個々の記者は「生活」を取らざるを得ないと思う。「記者はペンを取る、会社は記者の生活を守る」。そんな原則を理解した経営陣がいることが、よい新聞社の条件ではないか。
新聞と戦争について戦後いろいろな記事が書かれたが、今回の連載「新聞と戦争」は出色のできばえだ。過去の自らの活動を、驚くほど厳しく自己点検している。過去と同じわだちにはまりこまないために必要な作業だと思う。
引き続き勇気をふるって、自己点検を続けてほしい。
(聞き手・塩倉裕)
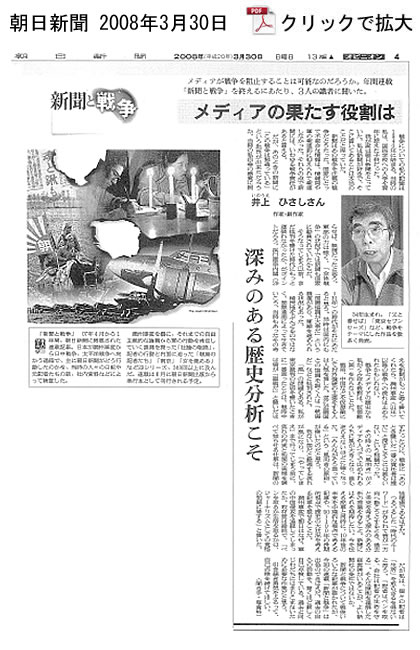
Tweet