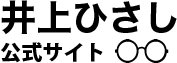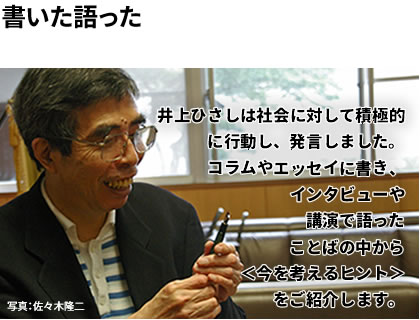![]() 1991年11月「中央公論」掲載
1991年11月「中央公論」掲載
『シャンハイムーン』谷崎賞受賞のことばより抜粋
魯迅の講義ノート
魯迅の五十六年の生涯を貫くものの一つに「一般論は危険だ」という考え方があったのではないかと、私は思う。「日本人は狡猾だ」、「中国人は国家の観念がない」、「アメリカ人は明るい」、「イギリス人は重厚だ」、「フランス人は洒落ている」という言い方は避けよう。日本人にも大勢の藤野先生がいる。中国人にも売国奴がいる。日本人はとか、中国人はとか、ものごとを一般化して見る見方には賛成できない。彼の膨大な雑感文には、この考え方がつねに流れている。火事場泥棒風に中国大陸に「進出」してくる日本を彼は心底から憎んだ。がしかし、晩年の九年間、国民党政府の軍警の目を避けるために、郵便物の宛先を内山完造が経営する書店にしていた。百四十の筆名を使って書き分けていた雑感文の原稿料の振込み先も内山書店だった。また、彼は五つも六つも病気を抱え込んでいたが(とくに胃をひどく損ねていた。少年時代から青年時代にかけて、唐辛子を食べすぎたのが病因の一つになっていたにちがいない)、主治医も日本人の須藤五百三だった。京彪之助さん(福井県立短期大学教授)の調査によると、須藤医院の、≪昭和十四年ごろ一日の患者数は一四〇人ないし一七〇人であった。≫(「須藤五百三――魯迅の最後の主治医」福井県立短期大学研究紀要第一〇号、昭和六十年三月)
かなり流行っていた病院であると思われるが、須藤院長は熱心に魯迅のところへ往診にでかけている。日に二度も魯迅を診て、過労から引っくり返ってしまったこともあったらしい。魯迅の絶筆は内山完造に宛てた走り書きの手紙であるが、それにはこう認めてある。
「……お頼み申します。電話で須藤先生に頼んでください。早速みて下さる様にと」
それから、魯迅のデスマスクをとったのも奥田愛三という日本人の歯科医だった。このように、臨終近い魯迅の周辺を日本人が守り固めていたのである。抗日統一戦線の政策を支持しながらも、良質の日本人がいることを知っていた魯迅も立派だが、当時の日本人の合言葉「不潔なシナ人」にとらわれることのなかったこれらの日本人もまた立派だった。
『井上ひさしベスト・エッセイ』(ちくま文庫)に収録

Tweet