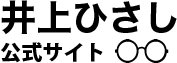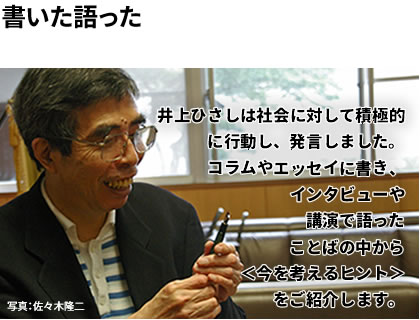![]() 2001年
2001年
生きる希望が「なにを書くか」の原点
対談集「話し言葉の日本語」より
■「テーマ」より「演劇的構造」をまず考える
百人、劇作家がいれば、百通りのテーマがあると思いますね。
僕の例で言いますと、正直に言いますが、戯曲を書こうと思ったときに、たとえば原爆をテーマにしようとか敗戦間際の大連を書こうとかといったテーマや思想や構想を最初にもって書き出すと、必ずと言っていいほど、失敗します。いや、これは、ほんとうです。
小説ですと、まずテーマがあって、それに沿って書き出すのは当たり前の方法論なんですが、芝居は、そうじゃないんですね。「演劇的仕掛け」とでも言いましょうか、舞台の上で、「こうなったらおもしろい」とか、「意外なところから登場する」とか、「お客さんとの約束ごとをどんどん破っていく」とか、そういった、「演劇でなければ表現できない構造」をまず考え、 そこから入っていくとおもしろい芝居になることが多いですね。
■書いているうちに、テーマが出てくる
僕の手の内を明かすとすると、こうなりますね。
まず、お客さんをどう騙せるかというのが、僕のスタートですね。ですから、最初の十分間くらいは、必ずお客さんと取引をします。「この芝居は、こういうルールで展開しますよ」と いう、ひとつの決まりを提示するわけです。これがうまくいくと、次が楽になります。
それでルールに慣れてもらって、お客さんのほうが、この後はこう進んでいくに違いないと思い始めたころから、少しずつ ルール違反をしていくんですね。それでグーッと違反をしてくると、謎が生まれるわけです。さらにそこに今度は、別のルールを放り込む。じつは、このルールというのは、よく考えてみると最初のルールのなかに含まれていたということがお客さんにわかったときが、ドンデン返しが成功したときなんですね。
こうした構造があったうえで、何を書くかということになるんですけど、大きなテーマを考えれば考えるほど、それをどう圧縮できるか、ねじ曲げられるかというあたりがいちばん苦しいですね。そこで悩んで、いわゆる悪魔といいますか、ひらめきが起こるのを待つわけです。
お客さんから見ますと、作者がこういうテーマで、こう書きますよと思いながら書いた芝居は、しばらくすると作者の意図が見え見えにわかってしまって、見ていてつまらないんです。だから、むしろ、作者が途中まで書いているうちに「ああ、そうか、俺はこれを書きたかったんだ」とわかるような作品は、観客の方でも、じつはそこまでなにもわからないわけですから、面白い作品になる可能性が高いということは言えますね。
■劇作は「希望をつくる」仕事
人生というのは九割九分までつらいことの連続だ というのが、僕の世界観です。
でも、その九割九分、つらい人生のなかで、そのなかにひとつでも希望があればそれにすがって生きることができるんですね。
お客さん同士が、寂しいけれど、つらいけれど、この芝居を見た瞬間だけでも、助け合って、すばらしい時間に変えてしまおうという気持ちになるんですね。そうした人たちにパワーを与えるのが、僕たちの 仕事だと思うんです。
その芝居自体が質が高くて、それでいておもしろい。おもしろいというのは、ゲラゲラ笑うことではなくて、 技巧的、思想的、構造的なことも含めた深い意味でおもしろい ということですけど、そうした芝居を観客の前にどう提供したらいいのか、それが結局、劇作家は「何を書くか」につながるのではないかと思うんですね。
「話し言葉の日本語」井上ひさし 平田オリザ(新潮文庫)より抜粋

Tweet